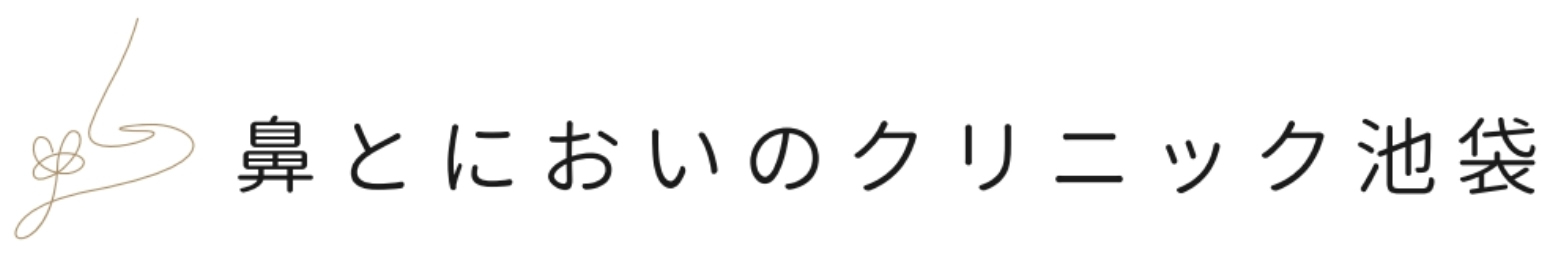【最新研究紹介】加齢によって悪化する嗅覚障害―その原因別に見た影響とは?
2025.06.29イントロダクション
「最近、においがわからない」「料理の味がしなくなった」と感じたことはありませんか?
嗅覚障害は、加齢に伴って自然に起こる変化に加え、鼻や脳の病気が原因となることもあります。特に風邪や副鼻腔炎のあとに「においが戻らない」といった相談が増えてきます。
嗅覚は、日常生活の安全(ガス漏れ、焦げなど)や食事の楽しみに大きく関わる感覚であり、その障害は生活の質を著しく低下させることがあります。
今回ご紹介するのは、「加齢が嗅覚障害にどのような影響を与えるのか」を病気の種類ごとに解析した最新の研究です。約2000人の患者データをもとに、どの疾患が加齢によって特に悪化するかが明らかにされました。
研究の背景と目的
嗅覚障害にはさまざまな原因があります。代表的なものとしては、以下が挙げられます:
- 非好酸球性副鼻腔炎
- 好酸球性副鼻腔炎
- ウイルス感染後の嗅覚障害
- 頭部外傷後の嗅覚障害
- 原因不明の嗅覚障害(特発性)
これらの疾患において、加齢がどの程度関与しているのかは、これまで十分に検討されていませんでした。
本研究では、年齢が嗅覚機能に及ぼす影響を、原因ごとに解析し、年齢に応じた診断や治療方針の参考となる知見を得ることを目的としています。
研究の方法
この研究は、1986名の患者データを用いた後ろ向き観察研究です。
対象疾患は以下の5つ:
- 非好酸球性副鼻腔炎
- 好酸球性副鼻腔炎
- ウイルス感染後の嗅覚障害
- 頭部外傷後の嗅覚障害
- 原因不明の嗅覚障害(特発性)
各患者の嗅覚は、「T&Tオルファクトメーター」という嗅覚検査で評価され、検出閾値(においを感じる最小濃度)と認識閾値(においを判別できる最小濃度)が測定されました。
患者は20歳代から80歳代まで10歳刻みの年齢群に分けられ、年齢と疾患との関連を統計的に分析。また、60歳未満と60歳以上での重度嗅覚障害の発生率についても解析が行われました。
結果
- 非好酸球性副鼻腔炎、ウイルス感染後嗅覚障害、特発性嗅覚障害では、加齢とともに嗅覚が有意に低下していました。
- 一方で、好酸球性副鼻腔炎および頭部外傷後の嗅覚障害では、加齢による嗅覚の悪化は明確ではありませんでした。
- 重度の嗅覚障害は、60歳以上の患者で有意に多く認められましたが、その傾向は疾患によって異なりました。
考察
本研究から、嗅覚障害の進行には「加齢」と「基礎疾患のタイプ」の両方が影響することが明らかになりました。特に、非好酸球性副鼻腔炎やウイルス感染後の嗅覚障害では、年齢が高くなるにつれて、においの感度が著しく低下する傾向があるため、高齢者の嗅覚ケアがより重要となります。
一方、好酸球性副鼻腔炎では、炎症そのものの影響が大きく、年齢による変化はあまり見られない可能性があります。このタイプでは、内視鏡下鼻副鼻腔手術や生物学的製剤(デュピクセント、ヌーカラ)など積極的な治療が有効とされており、早期に適切な診断と対応を行うことが求められます。
引用はこちらから
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40526035/
嗅覚障害・鼻づまりでお悩みの方へ
- 「においがしない」「食事が味気ない」と感じたら、放置せずにご相談ください。
- 当院では、においの検査「T&Tオルファクトメーター」、画像診断、血液検査を組み合わせて、原因を明らかにしたうえで、一人ひとりに合った治療方針を提案しています。
- 薬物療法で改善しない場合、全身麻酔下でマイクロデブリッターを用いた内視鏡下鼻副鼻腔手術を行っております。