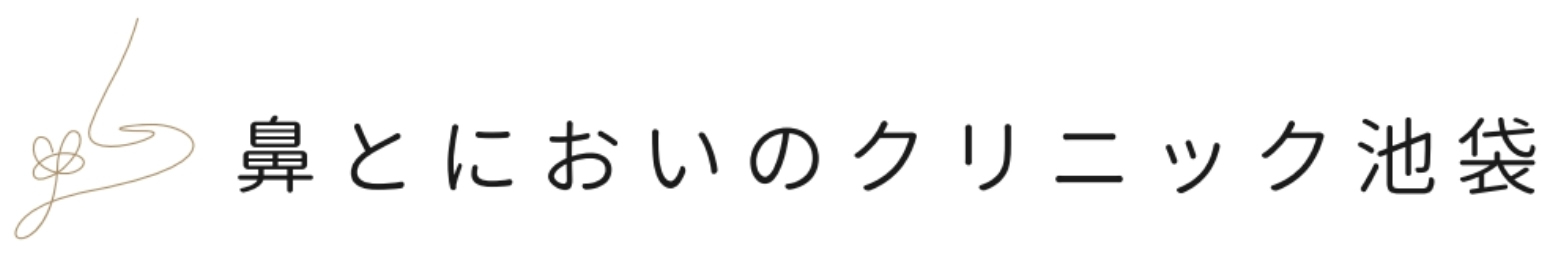【日本における鼻出血治療の全国調査から見えてきたこと】
2025.09.06イントロダクション
鼻出血は耳鼻咽喉科を受診するきっかけとして最も多い症状のひとつです。多くは自然に止まりますが、繰り返す場合や出血量が多い場合には医療的な処置が必要になります。特に冬場は空気が乾燥し、鼻の粘膜が傷つきやすいため、鼻出血で受診される方が増加します。
今回ご紹介する論文は、2025年に岡山大学の牧原靖一郎先生がご発表されたもので、日本全国の診療報酬データを解析し、鼻出血治療の傾向を明らかにした初めての研究です。治療の季節性や年齢分布、地域差が詳しく報告されており、耳鼻咽喉科診療における重要な知見となっています。
研究の背景と目的
鼻出血の治療には、止血用のガーゼを詰める方法と、出血点を焼灼する方法がよく用いられます。しかし、どちらの治療がどのような場面で多く行われているのか、全国的な実態はこれまで明らかにされていませんでした。
本研究は、鼻出血治療の季節的な傾向、年齢や性別ごとの特徴、さらに地域ごとの治療法の違いを調べることを目的としています。
研究の方法
研究には、2019年度から2022年度までの「国民健康保険診療報酬データベース」が用いられました。対象となったのは、鼻出血に対して以下の処置を受けた症例です。
- ガーゼパッキングによる止血
- 焼灼術による止血
これらの治療が、どの季節に、どの年齢層に、どの地域で多く行われているかが分析されました。
結果
- 治療件数
研究期間中に記録された件数は、ガーゼパッキングが 87万件、焼灼術が 52万件 にのぼりました。 - 季節性
いずれの治療法も、冬(12月〜2月)にピークを迎える季節的な傾向が認められました。 - 年齢分布
二峰性の分布を示し、小児と高齢者で発症が多い傾向がありました。また、全年齢層で男性に多い結果でした。 - 地域差
西日本ではガーゼパッキングが多く行われ、北日本では焼灼術がより多く行われていました。これは緯度や気候条件など、環境要因の影響を示唆しています。
考察
この研究は、日本における鼻出血治療の大規模な実態を明らかにした初めての報告です。季節や地域、年齢による違いがあることから、気候だけでなく、地域ごとの医療体制や診療習慣も治療法の選択に影響していると考えられます。
当院でも、患者さんを診察していると、鼻の粘膜が傷ついている所見は、冬に多く、特に乾燥や鼻のかみすぎによるものがよく見られます。鼻中隔弯曲症がある方は鼻づまりが強いために鼻をかむ回数が増え、粘膜が傷ついて出血しやすくなります。また、アレルギー性鼻炎をお持ちの方は粘膜が炎症で脆くなっているため、鼻血を繰り返すことがあります。
繰り返す鼻出血の背後には、副鼻腔炎や鼻中隔弯曲症といった構造的な問題が隠れている場合もあります。当院では、内視鏡検査やCTを用いた精密な診断により、原因を特定したうえで手術を含めた適切な治療をご提案しています。
まとめ
- 鼻出血は冬に多く、小児と高齢者で発症が多い
- 西日本ではガーゼ止血、北日本では焼灼術が多い傾向
- 鼻中隔弯曲症やアレルギー性鼻炎は鼻出血を繰り返す要因となる
鼻血が頻繁に出る、または止まりにくいといった症状でお悩みの方は、耳鼻咽喉科での精密検査をおすすめします。当院では、鼻の構造や炎症の状態を詳しく調べ、患者様一人ひとりに最適な治療を行っています。
引用はこちらから https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40445119/